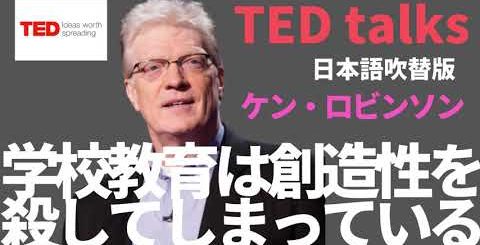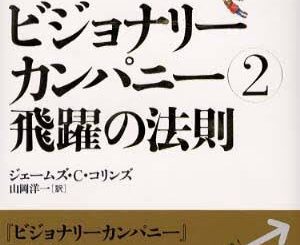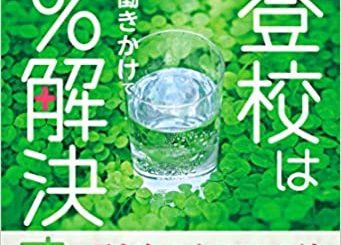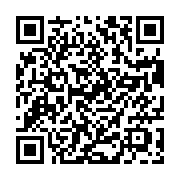地域の在り方がここに。「静岡方式」で行こう!!2を読んで
自由学校の場所探しに自分ごとのように全力で伴走してくださった、山梨女性起業家のドン(ぇ)、香さんからご紹介いただいた本です。
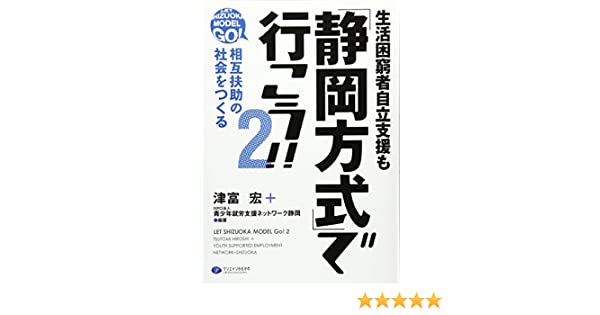
概要
若者就労支援のボランティア数名からスタートして、今や県内に500名のボランティアを抱えるまでに成長したNPO法人さんが、どのように仕組みを作り上げていったかが紹介されています。
このNPO法人(青少年就労支援ネットワーク静岡)さんの代表、津富宏さんが実践されている社会が、地域の「困りごと」を地域の皆で支え、繋がりの中で解決していくというものなのです。
市町村から受託事業を受けている有償ボランティアはその社会を築くためのきっかけづくりとして動くのみで、主体はあくまで無償ボランティアさん。
無償ボランティアさんが次から次へと世話を焼いて、全員でうわーっと困っている人を助けまくってしまうというものなのです。
なぜそんなことが出来てしまうかと言えば、無償ボランティアさん同士も支え合える仕組みだから。
自分が出来る範囲で誰かを助け続けていれば、いざ自分が困った時にも必ずみんなから助けてもらえる。
そんな安心感がこの社会を支えている気がします。
こんな社会こそが何よりもの社会保障なのではないでしょうか。
自由学校との関係は?
そうこんな社会こそが、私が自由学校の周りに作り上げたい社会なんです。
今は子ども達は守られています。
優しいスタッフ、手厚いケア、何も強制されない自由な時間、苦手な人には会わなくていい。
しかし、これがいつまでも続くでしょうか。
高校生になったら?社会に出るべき年齢になったら?
私たちはそこまで子ども達を守ることができません。
しかし、大人になるまでに地域と繋がっていれば…
- いつも草取りを手伝ってあげて、その代わりに野菜をくれる農家さん
- 急な梱包要員として時々手伝いにいく中小企業の社長
- 頻繁にご飯を食べにいって、悩みを聞いてくれる飲食店オーナー
こんな人たちと日常的に繋がって関わり合っていれば、いざ自分が社会に出る年齢になってどこの会社も元不登校児を受け入れてくれないなんてことになっても…
この人たちなら絶対助けてくれるじゃん。
「ぉー、困ってんのか。じゃあうちで働けよ」
って誰か言ってくれるじゃん。
子ども達が自由学校に在籍してるうちに、子ども自身にこういう大人との繋がりをたくさん作っていってもらうことを目標にしています。
この自由学校も場所の確保のために実に多くの起業家仲間が動いてくれました。
特に最初に書いた香さんに対しては本当に頭が上がりません。
でもどうしてこんなに助けてもらえたのかといえば、多分、私自身が前経営者のヘルプを受けて消滅しそうだった自由学校を救うために走り回っていたのを見てくれていたからだと思います。
この地域の為に必要な人材であると認めてくれたのではないかなと(勝手に)考えています。
自由学校の運営が落ち着いたら私もまたこの地域で困っている誰かの為に全力で伴走すると思います。
いいでしょ、こういう社会。
今ここにあるんですよ。
今の自由学校での課題
P35 止まらない、空き時間を作らない、たえず前に進む
既存の支援機関は、若者に対して「ゆっくり考える時間が必要」「まずは傷を癒すべき」としていますが、本書ではそれは的外れだと説いています。
これは私もすごく同感です。
人に考える時間を与えると、人は悩みすぎて足が止まってしまう。
悩みだす前にとりあえずやってしまえば、あとはなんとかなるものなんです。
今の自由学校は既存の支援機関そのものです。
子どもが落ち着ける居場所を作り、とにかく休ませる。
自由学校に来たばかりの子にはそういう時間も必要かもしれません。
でもあまり空き時間が長いと、立ち上がるための足の筋力を奪ってしまうのではないかと心配なのです。
定期的に学校に再チャレンジする機会を設けることは子どもにとって苦しみでしかないのか、それとも必要なことなのか。
ここは長いこと子どもたちを見てきたスタッフ、保護者の皆さんとじっくり話し合っていくべき課題だと感じています。
いや、自分でガンガン勉強進められる子ならほんと、学校行かなくていいんですけどね。
そうでない子は…やっぱり、学校が一番コスパいいんですよね。
P126 できるだけたくさんの人に会うことが大事
日本政策金融公庫でのセミナーで私の方から申し上げたことですが、「どんな状況になっても人と会うことだけは諦めてはいけない」のです。(コロナを除く)
本書でも繰り返し人と人との繋がりの大切さを説いています。
日本での困窮の原因もほとんどが孤立に起因しています。
持ち金の大小ではなく、人に頼れるかどうかが困窮を決定づけるのです。
自由学校の在籍児は、親御さんから「知らない第三者が苦手な子なので、よその人が入らない環境にしてほしい」との話が出る子が多いです。
私はこの考えが一番危険だと考えていて、自由学校を出た後に困窮する可能性を危惧してしまっています。
そしてそれら親御さんの意見を尊重して、閉じた世界にしてしまっている今の自由学校にも危険を感じています。
勉強なんてできなくていい、いい学校なんて出なくていい、でも人と繋がることを拒否するのだけはいけません。
ここも今のスタッフや親御さんと話して理解してもらって、少しずつ地域の人と触れ合うことに子どもたちに慣れてもらわなくてはいけないと考えています。
 | 生活困窮者自立支援も「静岡方式」で行こう! 2 相互扶助の社会をつくる 新品価格 |